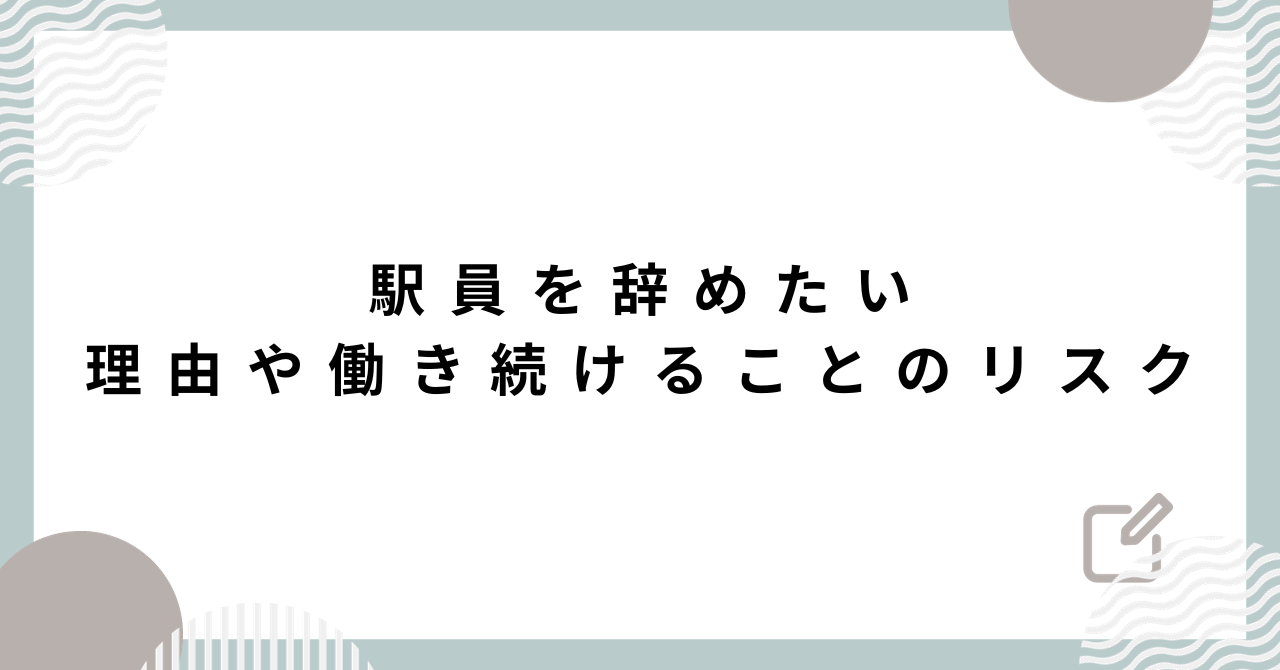勤務体制に体が慣れなくて、毎日きつい…

駅員の仕事を始めてから、心が休まらない…
駅員の仕事がつらくて辞めたいという声はネット上で多数見受けられます。実際に、精神的な苦痛や疲労の蓄積などで退職・転職を考えている人もいるでしょう。
心身ともに限界だと感じながら、働き続けると体を壊す、メンタル不調などで今後の人生に悪影響を及ぼすかもしれません。

この記事では、駅員を辞めたいと感じる理由と働き続けたときに生じるリスクを解説します。駅員を辞めようか迷っている人はぜひ参考にしてみてください。
駅員を辞めたいと感じる理由

駅員を辞めようか考えている人の多くは、業務内容や職場環境に対して不満を挙げています。駅員を辞めたいと感じる理由を5つ解説します。
クレーム対応
クレーム対応は駅員を辞めたいと感じる代表的な理由の一つです。駅員として働くなら、事故や天候による遅延を始めとした理不尽なクレームに耐えなくてはいけません。
自分に非がなくても、「大事な会議に遅れたら、どう責任取ってくれるんだ!」「いつまで待たせるつもりなんだよ!」と口汚く罵られます。ひどいときは、殴られる場合もあります。
泊まり勤務
駅員は朝から翌日の朝まで24時間勤務する「泊まり勤務」が基本です。
仮眠時間は5時間ほどありますが、シャワーや就寝前と起床後の身支度の時間を差し引くと、実際の睡眠時間は5時間を下回ります。事故対応やお客様対応がある場合は徹夜になることもあります。
人間関係が築けなくてつらい
現場配属された際、最初の1か月間は指導員が出勤から退勤までマンツーマンで研修を行います。
指導員と良好な人間関係が築けなかったとき、毎日の勤務がつらくなります。とくに怖くて厳しい指導員に当たった場合、精神的な苦痛は非常に大きくなります。
また、縦社会の文化が色濃く残っているため、若い人に対して「上の言うことは絶対!」と横柄な態度をとる先輩、上司もいます。
人身事故の対応
駅員は人身事故が発生した際、すぐに現場に行き、遺体回収をします。遺体見るも絶えない凄惨な状況ですが、目を背けずに回収しなくてはなりません。
人によっては、トラウマになり、食欲がわかなくなったり、ふとした瞬間に事故現場を思い出してしまうこともあるはずです。
ルーチンワーク
事故を始めとしたイレギュラーなことが発生しない限りは、駅員の仕事は基本的にルーチンワークです。
精算や駅周辺の案内などをする改札業務やホームの安全確認などの業務を淡々とこなすだけです。
「今の仕事は、誰の役に立っているのか分からない…」「今後のキャリアに活かせる経験を積んでいるのだろうか?」などと同じ作業を繰り返す日々に疑問を持つ人も多くいます。
駅員を辞めたいと感じながら働き続けるリスク
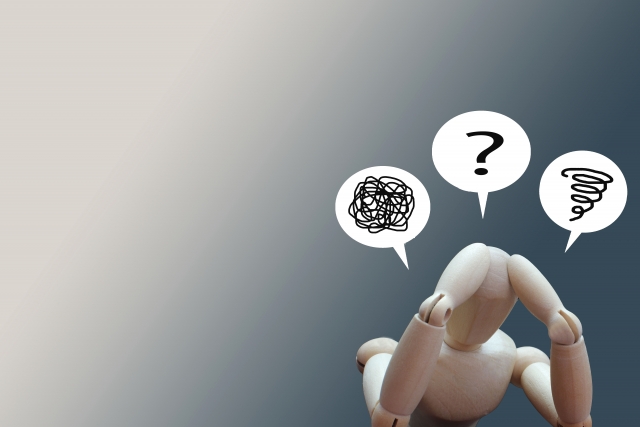
駅員を辞めたい理由として、業務内容や職場環境による心身への大きな負担が見受けられました。また、単調な仕事への不満も辞めたい理由として挙げられていました。
こちらでは、辞めたいと感じながらも駅員の仕事を続けることで生じる3つのリスクを解説します。
体を壊す
泊まり勤務が基本である駅員は睡眠不足になりがちなため、体を壊しやすくなります。
泊まり勤務の際に、取れる睡眠時間は長くても3〜4時間程度で、働く世代に必要な睡眠時間の6〜9時間を下回っています。
厚生労働省によると、睡眠時間が6時間未満の人は死亡や疾患のリスク増加と関連しており、死亡は1.12倍、糖尿病は1.37倍増加するそうです。
勤務体制上、睡眠時間が短くなりがちな駅員は、体を壊すリスクが他の仕事より高いと言えます。
メンタル不調になる
駅員はメンタルに負担をかける要因が多くあります。
電車の遅延が発生したとき、イライラしている多くの乗客に口汚く罵倒されても、反論せず、ひたすらに謝り続けなければなりません。
また、縦社会が残っている職場環境では、先輩社員や上司、指導員との関わりに注意を払う必要があります。人身事故の対応を任されたとき、遺体回収がトラウマとなり、日々の生活がつらくなる可能性もあります。
駅員はクレーム対応を始めとしてメンタル不調を患う要因が、ほかの仕事より多いと言えます。
転職が難しくなる
車掌、運転士へとキャリアアップしたい人のように駅員として働く目的が明確ではないなら、早めの転職がおすすめです。
転職は年を重ねるほど、高い専門性やマネジメント能力が求められるようになります。
駅員の仕事を通じて、丁寧な言葉遣いや不測の事態への対応力が身に付きますが、基本ルーチンワークでほかの業種・職種でも活かせるスキルを磨くのは難しいです。
駅員として働く目的を見いだせないなら、早めに転職活動をしたほうがいいでしょう。